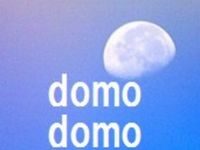新設住宅着工戸数が大きく減少している。過去の統計を見ると、これまで年間100万戸を下回ることがなかった。しかし、2009年は住宅需要が激減し、年間80万戸に達するかどうかというペースになっている。政府は景気刺激策として住宅減税なども行っているが、その効果も限定的のよう。住宅着工戸数は景気のバロメーターでもある。今後の動向には注意が必要だ。
新設住宅着工戸数が大きく減少している。過去の統計を見ると、これまで年間100万戸を下回ることがなかった。しかし、2009年は住宅需要が激減し、年間80万戸に達するかどうかというペースになっている。政府は景気刺激策として住宅減税なども行っているが、その効果も限定的のよう。住宅着工戸数は景気のバロメーターでもある。今後の動向には注意が必要だ。
 国土交通省が公開している新設住宅着工戸数の推移のグラフ。平成19年度(2008年3月期)は103万戸にまで落ち込んでいることがわかる。
国土交通省が公開している新設住宅着工戸数の推移のグラフ。平成19年度(2008年3月期)は103万戸にまで落ち込んでいることがわかる。
2009年以降も回復は期待できない状況となっており、今期は過去最低を記録する可能性が高くなっている。
しかし、かねてより「年間80万戸が妥当な数値」だという論者もいる。
その論点は
①実需としての住宅(真の需要)
②空き家とのバランス(供給構造)
の2点である。
①実需としての住宅(真の需要)は、実際の着工戸数よりも少ないということ。新設住宅着工戸数の内容を見ると、ざっくりと貸家:3割、分譲住宅:3割、持ち家:4割の3つにわけられる。このうち建設着工時に確実な実需はほぼ「持ち家」だけで、「貸家」も「分譲住宅」も入居者が決まっているわけではない。特にアパートやマンションなどの貸家は、地主が相続税の節税対策のために建てる例が多く、地域の実情を反映したものとは限らない。さらに都市部のマンションは投機的な売買も多く、実需とは乖離している点も否めない。
②空き家とのバランス(供給構造)は、世帯数と総住宅数を比較するとわかりやすい。現在、日本の世帯数は4999万世帯。一方、総住宅数は5759万戸であり、世帯数と比較すると供給過剰になっていることがわかる。実際に総住宅数5759万戸のうち、空き家は756万戸となっており、空き家率は13.1%と過去最高になっている。(出典は総務省)
つまり、日本の住宅は実需を超えた供給が常態化していたわけである。
住宅も構造調整局面にならざるを得ないだろう。
今後は、空き家を流通させるマーケットがますます機能していくことで身の丈にあった住宅を選択できるようになるだろう。そして、持ち家は、ライフスタイルに適した高品質な注文住宅を選択する傾向が強くなっていくのではないだろうか。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。
保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など
会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。
お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。
【反応していただけると喜びます(笑)】
記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。
遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。
facebook https://www.facebook.com/tohdamikio
ツイッター https://twitter.com/tohdamikio
LINE https://lin.ee/igN7saM
チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda
また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。
※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)
※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってください(笑)