 2月19日午後の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが上昇し、一時前日比0.005%高い1.435%と、約15年ぶりの高水準になりました。同時に日米金利差が縮小するという予測から円高ドル安が進行しました。
2月19日午後の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが上昇し、一時前日比0.005%高い1.435%と、約15年ぶりの高水準になりました。同時に日米金利差が縮小するという予測から円高ドル安が進行しました。
この背景には、日本銀行(以下、日銀)が2024年3月にマイナス金利政策を解除し、政策金利を0~0.1%に引き上げた後、2024年8月には0.25%、2025年1月には0.5%へと段階的に利上げを実施したことが大いに関係しています。さらにこの春先にも0.75%に利上げを匂わすような日銀幹部からの発言がありました。
この一連の動きは、持続的なインフレ率の上昇や賃金の増加を背景に、金融政策を正常化することを目的としています。
このような環境変化をふまえたうえで、一般市民としては個人資産をどのように守り運用していくのがいいかを考察してみました。
これから日本の金融や経済はどうなるのでしょうか

では、こうした金利上昇は、私たちの生活や経済にどのような影響を与えるのでしょうか?ここでは、家計、企業、政府、金融市場などの各方面への影響について、分かりやすく解説します。
家計への影響
住宅ローンの負担増
長期金利が上昇すると、住宅ローン金利も上がる傾向にあります。特に変動金利型の住宅ローンを利用している方は、毎月の返済額が増える可能性があります。これにより、家計の負担が大きくなることが懸念されます。
預貯金の利息アップ
一方で、預貯金の金利も上昇するため、貯金が多い人にとってはプラスの影響があります。特に、定期預金を活用している方にとっては、利息収入の増加が期待できます。ただし、負債を多く抱える現役世代にとっては、住宅ローンや教育ローンなどの返済負担が増えるため、全体的にはマイナスの影響が大きいと考えられます。
企業への影響
借入コストの増加
企業も資金を銀行から借りて事業を運営しているため、金利が上昇すると借入コストが増加します。特に、多額の借入をしている企業にとっては、利払い負担が重くなるため、設備投資や新規事業の展開を控える動きが出るかもしれません。
影響を受けやすい業種
・ 中小企業:資金調達を銀行借入に依存している企業が多く、影響を受けやすい
・ 非製造業:特にサービス業など、利益率が低い業種では、コスト増加が経営を圧迫する可能性あり
政府への影響
国債の利払い負担の増加
日本の政府債務残高は、2023年末時点で名目GDPの265%に達しています。長期金利が1%上昇すると、国債の利払い費用が年間で約3.2兆円増加するとの試算もあります。このため、政府の財政負担が重くなり、財政健全化の課題がさらに深刻化する可能性があります。
財政政策への影響
利払い費用の増加により、政府が行う社会保障や公共投資などの政策に影響が及ぶ可能性があります。将来的には、増税や歳出削減などの対策が求められるかもしれません。特に消費税増税について議論になるかもしれません。
金融市場への影響
為替市場:円高圧力が強まる
金利上昇は、為替市場にも影響を及ぼします。特に、日米の金利差が縮小すると、これまで円を売ってドルを買っていた投資家が円を買い戻す動きが強まり、円高が進む可能性があります。円高になると、輸出企業にとっては海外での競争力が低下し、企業業績に悪影響を及ぼすことが考えられます。
2024年以降は、1ドル=160円を超えるような推移をしていた時期もありますが、日本の長期金利上昇を受けて1ドル=150円前後に向かう円高傾向になっています。
株式市場:企業収益の悪化で株価が下落する可能性
金利が上昇すると、企業の借入コストが増加し、利益が減少する可能性があります。その結果、投資家が企業の将来の収益を見込んで投資する株式市場では、株価が下落する要因となることが考えられます。
今後の政策対応
日銀の方針
日銀は、物価の動向や賃金の上昇率を注視しながら、段階的な利上げを進める方針です。IMF(国際通貨基金)の報告によると、日本の中立金利(景気を過熱も冷却もさせない適切な金利水準)は**1%から2%**と推定されており、2027年までにその水準に達する可能性があるとされています。
政府の対応
政府は、財政健全化を進めるために、歳出の見直しや税制改革などの対応を求められる可能性があります。特に、社会保障費の増大や少子高齢化の進行により、財政の持続可能性を確保するための議論が重要になってきます。
新NISA初心者向けポートフォリオ戦略の基本
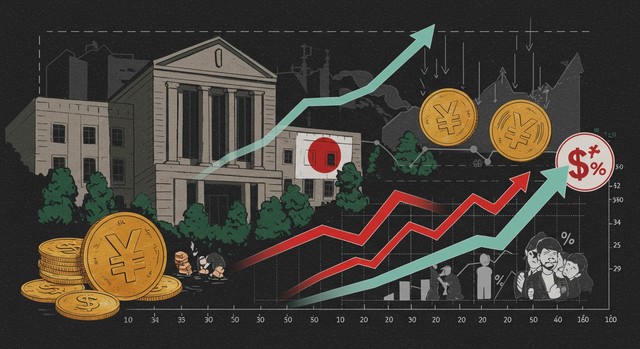
このような環境変化の中、一般市民(個人投資家)としてはどのようにして個人資産を守り運用していくのがよいでしょうか。
生成AIによる回答は以下のとおりです。
まずは3つの基本原則を確認しましょう
3つの基本原則
長期視点:5~10年単位での資産形成を意識
分散投資:資産クラスと地域を分けてリスク軽減
積立投資:毎月一定額を自動で投資
「長期、分散、積立」というのが基本です。
新NISA活用のポイント
年間120万円枠:一般枠(上限40万円)とつみたて枠(同80万円)を併用
非課税期間:最長20年間の税優遇(売却益・配当金非課税)
手数料抑制:信託報酬0.1%以下の低コスト商品を優先選択
具体的な運用ステップ
月5万円:つみたてNISAで米国株ETFを自動積立
年40万円:一般NISAで日本株ETFを一括購入
毎年見直し:資産比率のズレを5%以内に調整
注意点と対策
為替リスク:外貨建て商品はヘッジありを選択(例:為替ヘッジ付き米国株ETF)
暴落時の対応:相場下落時は通常通り積立継続(ドルコスト平均法効果)
流動性確保:投資資金とは別に生活防衛資金(3~6ヶ月分)を普通預金で確保
初心者向け推奨商品例
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
楽信投信 全世界株式インデックス
iShares コア トピックスETF(1475)
ポートフォリオの一例
| 資産クラス | 割合 | 具体例 |
|---|---|---|
| 日本株式 | 40% | 東証ETF(TOPIX連動型) |
| 米国株式 | 30% | S&P500連動型ETF |
| 先進国株式 | 20% | MSCIワールド指数連動型 |
| 債券/REIT | 10% | 国内外債券ETF・不動産投信 |
投資開始後3年間は「買い増しのみ」を基本とし、複利効果を最大限活かすことが重要です。最初の1年は「観察期」と位置付け、市場変動に慣れる期間と捉えましょう。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。
保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など
会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。
お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。
【反応していただけると喜びます(笑)】
記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。
遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。
facebook https://www.facebook.com/tohdamikio
ツイッター https://twitter.com/tohdamikio
LINE https://lin.ee/igN7saM
チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda
また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。
※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)
※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってください(笑)
