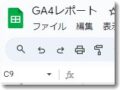中小企業はDX推進が遅れていますので対応の強化が必要です。今回は運送業に注目しました。
中小企業はDX推進が遅れていますので対応の強化が必要です。今回は運送業に注目しました。
よくある事例として「FAXや電話での受注」「メモなど手書きが多い」「高額のシステムはあるものの自社の業務に適合しないので使えない」「エクセルで管理しているが重複が多くて困っている」というような課題を抱えている中小企業を想定して解決策を考えてみました。
中小運送業のDX推進について
中小運送業の悩み(事例/ケーススタディ)
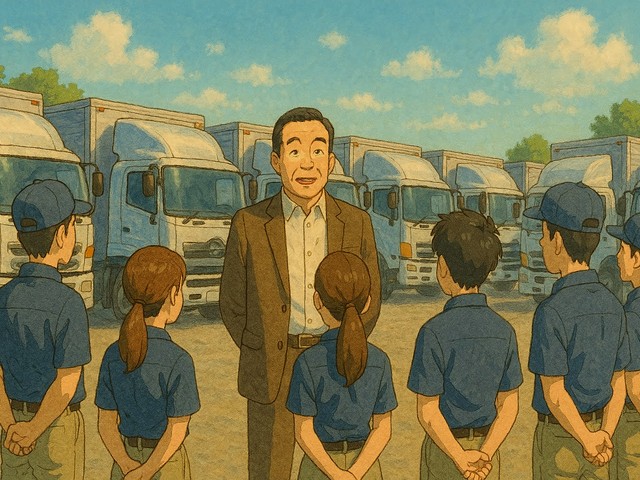
この運送会社は中小企業で、従業員30人以下、トラックは20台程度です。
現状の業務は紙やクローズドなエクセルや別途の販売管理システムになっていてつながっていません。
得意先からの依頼は電話やFaxおよびメールなどバラバラです。
受注管理と配車管理はエクセルですがうまく連動できていません。請求書発行のシステムも別途です。
なんとかDX化を図りたいという経営者からの希望があります。
条件というか希望としては
・開発費が100万円以上もかかることはやりたくない
・月々のコストで万円単位になるようなサブスクには入りたくない
・表計算ソフトには慣れているのでこの応用をしたい
・外注せずに社内の工夫で改善したい
ということでした。
このようなケースの要望にどのように対応するかについて、生成AIを活用し対策案を検討しました。主にChatGPTのDeepResearchを使いましたが、他の生成AIサービスも併用しファクトチェックなどをしました。
以下はその内容です。参考になれば幸いです。
今、運送業界が直面している4つの大きな環境変化
1.深刻化する労働力不足
ドライバーの高齢化が進む一方で、若年層の参入は減少傾向にあります。さらに、2024年から施行された労働時間の上限規制(年間960時間の時間外労働制限)により、ドライバーの確保が難しくなり、「輸送難」と呼ばれる事態が一部地域で発生しています。働きやすい環境整備が急務ですが、すぐに解決するのは難しい状況です。
2.環境規制の強化
カーボンニュートラルの目標に向け、運送業界でもEVトラックや燃料電池車の導入、モーダルシフト(鉄道や船舶への切替)が求められています。設備投資やインフラ面での負担は大きく、中小企業には対応が難しい面もあります。
3.デジタル化(DX)の加速
配車や運行の管理において、デジタル技術の導入が進んでいます。AIによる最適配車、動態管理、無人化・省人化の実証実験なども進行中です。とはいえ、中小企業にとっては、コストや人材の問題から導入のハードルが高いという現実もあります。
4.物流法改正による荷主責任の強化
物流の効率化に向けて、荷主側にも協力責任が課されました。非現実的な納期指定や空車前提の発注は問題視されており、荷主との関係にも変化が求められています。

中小運送業特有の課題とその背景
-
コスト負担の増加
燃料価格の上昇やEVトラック・倉庫設備の更新といった環境対応投資が重くのしかかり、資金力の乏しい中小企業にとっては大きな負担です。 -
業務効率の低さ
短納期・小口配送への対応が求められる一方で、配車や積載の効率が悪く、作業が煩雑になりがちです。これが結果として、人手不足をより深刻化させる要因ともなっています。 -
人材育成と技能継承の遅れ
ドライバーの高齢化により、長年のノウハウを若手に引き継ぐ体制づくりが急務ですが、整備が進んでいない企業も多く、新技術導入にも差が生まれています。
求められる対策と前向きな取り組み
このような厳しい状況においても、デジタル技術の活用や環境対応の工夫によって乗り越える道があります。
-
DXの推進
クラウド型の配車管理、AIを活用したルート最適化、IoTによる車両管理など、低コストで導入できるツールの活用が注目されています。 -
共同配送やモーダルシフトの活用
同業者との連携による共同配送や、幹線輸送に鉄道・船舶を活用することで、コストと環境負荷を同時に削減するモデルが拡大しています。 -
労働環境の改善
働きやすい職場づくりとして、待遇の見直しや多様な雇用形態(パートタイム、シニア採用など)の導入が求められています。

だからこそ、今「業務の見直し」が重要です
上記のような背景から、中小運送業では業務効率化と情報共有の仕組み作りがこれまで以上に重要になっています。
そこで本提案では、多くの方が使い慣れたGoogleスプレッドシートを活用して、低コストで始められる業務改善の方法をご紹介いたします。特別なIT知識がなくても始められるステップ形式で、業務の見える化と効率化を進めていきましょう。
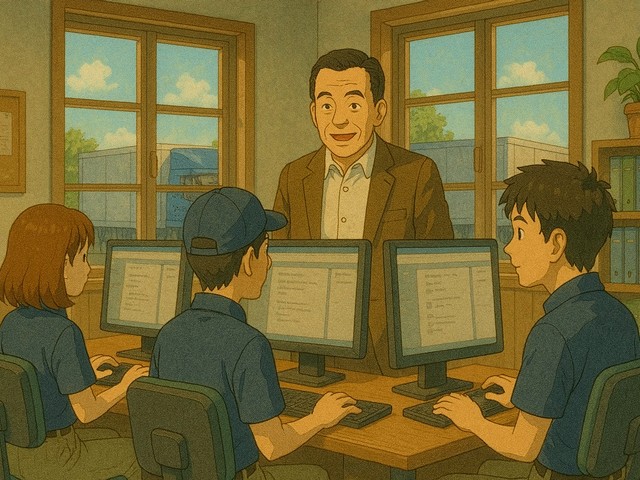
Googleスプレッドシートで進める、業務の効率化とDX(デジタルトランスフォーメーション)
はじめに:業務改善の必要性とは?
日々の受注や配車、請求業務において、次のようなお困りごとはありませんか?
-
情報があちこちに分散していて全体が把握しづらい
-
同じ内容を何度も手作業で入力する手間
-
情報共有がうまくいかず、ミスや見落としが心配
こうした課題に対し、本提案では、特別なシステムを導入せずに、Googleスプレッドシートを活用することで、業務の効率化とミスの削減を図る方法をご紹介します。操作に慣れた方が多いスプレッドシートなら、導入のハードルも低く、無料からでも始められます。
よくある課題と目指す姿
現在の課題:
-
情報がバラバラ:受注情報が紙メモ、FAX、メール、Excelなどに分かれていて把握が困難。
-
手作業の限界:転記作業が多く、入力ミスや漏れの原因に。
-
非効率な流れ:受注から配車、請求へと情報が連携されておらず、手間と時間がかかる。
目指す方向性:
-
情報の一元化:スプレッドシート上に情報を集約し、誰でも最新状況を把握できるように。
-
作業の自動化:関数を使った自動転記などでミスや手間を削減。
-
効率的な連携:受注から請求までの流れをスムーズに連動。
-
低コストで導入可能:無料アカウントでも活用でき、必要に応じて有料プランへの拡張も検討可能です。
改善のステップ(Googleスプレッドシート活用法)
Googleスプレッドシートは、Googleが提供しているクラウド上で動く表計算形式のソフトウェアです。無料でも使い始めることができますし、応用できるテンプレートも多数あります。
ステップ1:受注情報を一元化
「受注受付シート」にすべての受注内容を集約。重複しない「受注ID」を設定し、入力項目のルールを統一します。
ステップ2:配車管理をデジタル化
「配車管理シート」を作成し、VLOOKUPなどの関数で受注情報を自動表示。ドライバーや車両などはプルダウン形式で簡単に入力できます。
ステップ3:請求データを効率よく作成
配送完了データを抽出し、請求情報を自動集計。CSVで出力し、「弥生販売」などの既存システムに取り込むことも可能です。
ステップ4:段階的に定着を図る
まずは一部の業務から始め、操作に慣れてからスプレッドシート中心の運用へ移行します。
便利なスプレッドシートの機能(おすすめ機能)
-
VLOOKUP/XLOOKUP:自動で情報を表示
-
SUMIF:条件ごとの金額集計に便利
-
入力規則(プルダウン):入力ミスの防止
-
フィルタ・スライサー:必要なデータをすぐに表示
-
条件付き書式:進捗や対応状況を色で可視化
-
ピボットテーブル:集計や傾向分析が簡単
-
IMPORTRANGE:別シートの情報も一元管理
-
リアルタイム共有:複数人で同時に編集・確認が可能
応用:Google Apps Script(GAS)の活用
より高度な業務自動化を目指す場合には、Google Apps Script(GAS)を使うことで、定型作業の自動化が可能です。プログラミングの知識が必要ですが、外部の専門家へ相談するのも一つの方法です。
データの流れと既存システムとの連携
-
受注 → 配車 → 請求 の一連の流れを受注IDで紐づけ
-
各ステータス(受注済・配車済・請求済など)を管理
-
弥生販売などの販売管理システムとのCSV連携で請求業務もスムーズに
スムーズな運用のための工夫
-
簡単な操作マニュアルの作成
-
テンプレートの活用
-
Googleドライブでのファイル管理ルールの整備
-
社内での共有・勉強会の実施
-
アクセス権限の適切な設定(セキュリティ対策)
期待される効果
-
業務時間の短縮
-
ミスの大幅削減
-
情報共有の円滑化
-
システム導入費用の削減
-
経営判断に役立つデータの蓄積と分析が可能
-
段階的な業務改善による定着と成長
具体的なスプレッドシート導入ステップ

ステップ1:受注受付スプレッドシートの作成
目的:
受注情報を一本化し、すべての依頼内容をクラウド上で管理できるようにする。
実施内容:
- Googleスプレッドシートで「受注一覧」シートを作成
- 入力項目例:受注ID、依頼日、得意先名、配送先、荷物内容、希望納品日、特記事項など
- 受注IDは自動連番に(関数で「=ROW()-1」などを活用)
- 電話・FAX・メールなど形式に関係なく、すべての依頼をこのシートに転記
- 入力欄には入力規則(ドロップダウンリスト)を活用して誤入力を防止
ステップ2:配車管理シートの構築
目的:
受注情報をもとに、効率よくトラックとドライバーを割り当てる。
実施内容:
- 「配車管理」シートを新規作成
- 入力項目例:配車日、受注ID、ドライバー名、車両番号、出発時間、到着時間など
- VLOOKUP関数を使い、受注IDを入力するだけで配送先や荷物情報を自動表示
- ドライバー名や車両番号にはデータバリデーションで選択式入力を設定
- 配車担当者が視覚的に分かりやすいように、色分けや条件付き書式も活用
ステップ3:請求データの整備とCSV出力
目的:
配送完了した受注に基づいて、請求書データを整備し、弥生販売に連携する。
実施内容:
- 「請求データ」シートを作成
- 受注一覧から配送済み案件だけを抽出(FILTER関数などを活用)
- 得意先コード、金額、日付など弥生販売用の項目を整備
- GASを活用してCSV出力用ボタンを設置(自動でダウンロード保存)
ステップ4:ステータス管理と業務の見える化
目的:
配車や請求の進捗を把握しやすくし、漏れや遅れを防ぐ。
実施内容:
- 「受注一覧」シートに「配車済」「請求済」などのチェック欄を設置
- COUNTIF関数で未処理件数の集計欄を設ける
- 条件付き書式で未対応案件を赤色表示
- ピボットテーブルを使い、月次の受注件数や配車件数の集計を表示
ステップ5:Google Apps Script(GAS)の活用(応用編)
目的:
業務をさらに効率化し、自動化を実現する。
実施内容:
- 定期的なバックアップ:スプレッドシートを日付付きで自動保存
- ボタンクリックでCSV出力:請求データを自動でCSV形式に変換し保存
- 入力補助:受注ID入力時に必要な情報を自動補完
- 将来的にはSlackやLINEへの通知機能も導入可能 ※ GASはスプレッドシートメニューから「拡張機能 → Apps Script」で設定可能
ステップ6:運用ルール・マニュアルの整備
目的:
誰でも使えるようにルール化し、属人化を防止する。
実施内容:
- Googleドキュメントで操作マニュアルを作成(図解付き)
- 「テンプレート」フォルダをGoogleドライブに設置し、毎月コピーして使用
- 月1回の使い方共有ミーティングを実施し、改善提案を反映
ステップ7:弥生販売との連携方法
目的:
作成した請求データをスムーズに弥生販売に取り込む。
実施内容:
- 請求CSV出力フォーマットを弥生販売の形式に合わせて作成
- 得意先マスタをスプレッドシートに読み込み、得意先名選択時にコードが連動
- 請求締日にCSVファイルを出力し、弥生販売のインポート機能で登録
まとめ:期待される効果
- 全業務をGoogleスプレッドシートで一元管理することで、紙やバラバラのExcelファイルから脱却
- 情報共有のスピードが上がり、ミスや漏れが減少
- 初期費用ゼロ、月額費用ゼロで段階的なDXを実現
- 将来的にはGAS活用でさらなる自動化も可能
Googleスプレッドシートは無料で十分?有料版導入の考え方
Googleスプレッドシートは、Googleアカウントさえあれば無料で利用できるため、導入コストをかけずに業務改善を始めるには最適なツールです。実際、多くの中小企業が無料版からスプレッドシート運用をスタートし、必要に応じて機能を拡張しています。
無料版でできること
-
スプレッドシートの作成・編集・保存
-
複数人でのリアルタイム編集・共有
-
コメントや履歴機能を活用した業務連携
こうした基本機能だけでも、受注管理・配車表・請求データ作成など、日常業務の多くをカバーできます。まずは無料版で十分に運用可能かどうかを確認するのがおすすめです。
有料版(Google Workspace)を導入するとどうなる?
Google Workspace(旧G Suite)に移行すると、以下のようなビジネス向けの強化機能が利用できるようになります。
-
独自ドメインのメールアドレス(例:info@○○.com)
-
大容量クラウドストレージ(ユーザーごとに30GB〜5TB)
-
高度なセキュリティ機能(管理権限・データ保護・暗号化など)
-
チーム共有ドライブや共有カレンダー
-
24時間サポートへのアクセス
-
ビジネス利用に適した管理・連携機能
特に、組織全体でデータ共有を安全に行いたい場合や、より多くのファイル・データを扱う必要がある場合には、有料版の導入が効果的です。
Google Workspaceの有料契約は1アカウントあたり月額800円からです。
管理者だけ有料にすることはできるの?
はい、技術的には可能です。
管理者1人がGoogle Workspace契約を行い、他のメンバーが無料アカウントを使って共同作業する運用もできます。
ただし、次のような点にご注意ください:
-
無料ユーザーは、有料機能(ストレージ拡張、管理機能など)を利用できません
-
管理者アカウントにのみ機能が集中するため、チーム全体の運用効率が低下する可能性があります
運用スタイルに応じたおすすめの導入方法
| 運用規模 | 推奨スタイル |
|---|---|
| 初期・小規模運用 | 無料アカウントのみでスタート。スプレッドシートの基本機能で十分対応可能です。 |
| 段階的な拡張を検討中 | 管理者のみ有料契約をし、必要に応じて有料アカウントを段階的に追加する形も可能です。 |
| 中長期的に安定運用したい場合 | 全員をGoogle Workspace環境に統一することで、セキュリティやストレージの一元管理が可能になります。 |
無用版で試用してから有料版利用を検討する
現在の業務に対して「無料版で足りるか」「ビジネスの成長に耐えうるか」を判断しながら、段階的に導入を進めていくことがポイントです。
最初は無料で試し、使い勝手や運用効果を実感したうえで、必要に応じて有料版へのステップアップを検討していきましょう。
最後に

Googleスプレッドシートは、使い方次第で大きな可能性を秘めた業務改善ツールです。業務効率化・DX推進の一助となるのは間違いありません。
まずは小さな一歩から始めてみるのは有効です。チャレンジしてみませんか?

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。
保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など
会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。
お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。
【反応していただけると喜びます(笑)】
記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。
遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。
facebook https://www.facebook.com/tohdamikio
ツイッター https://twitter.com/tohdamikio
LINE https://lin.ee/igN7saM
チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda
また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。
※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)
※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってください(笑)